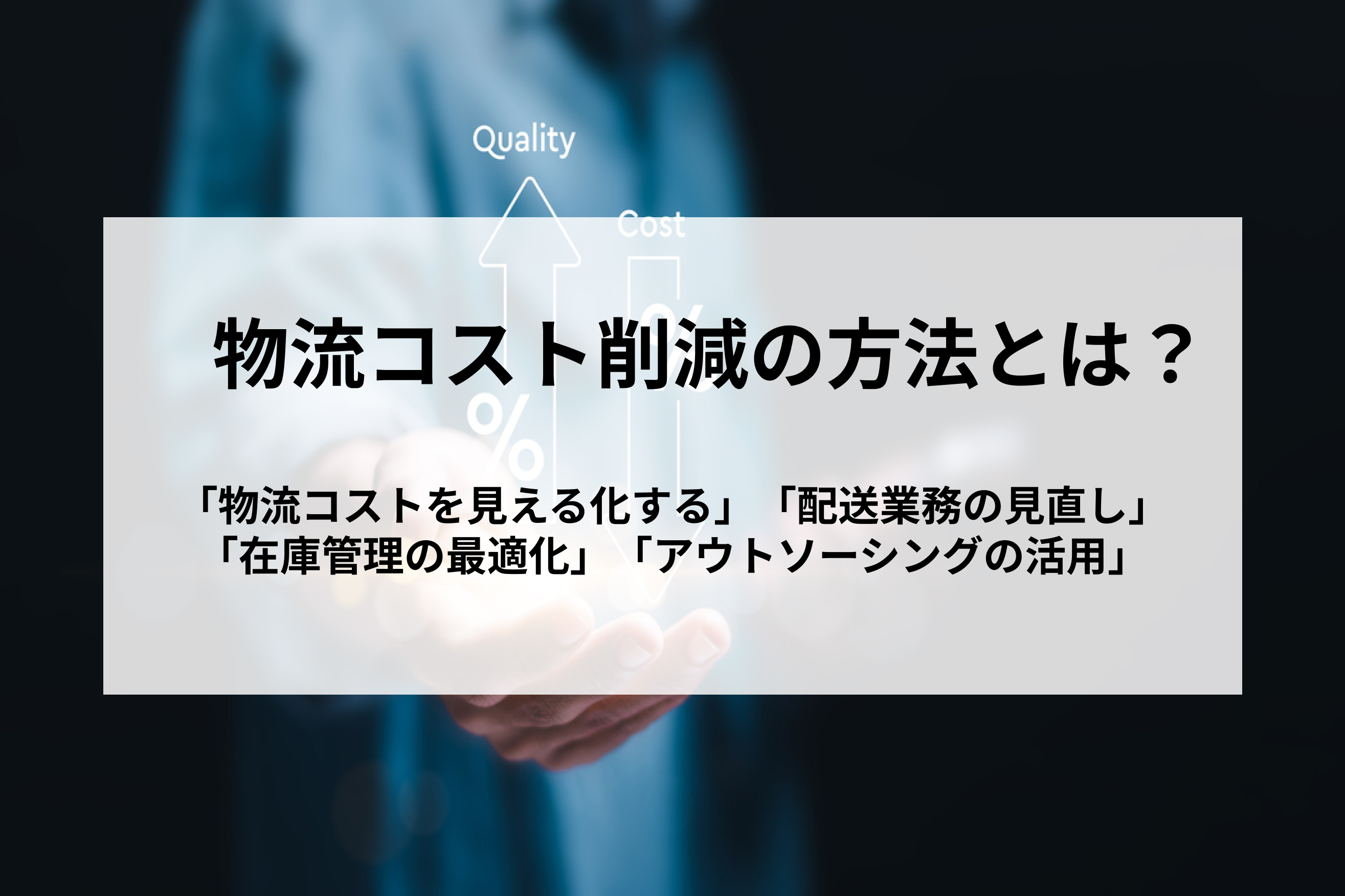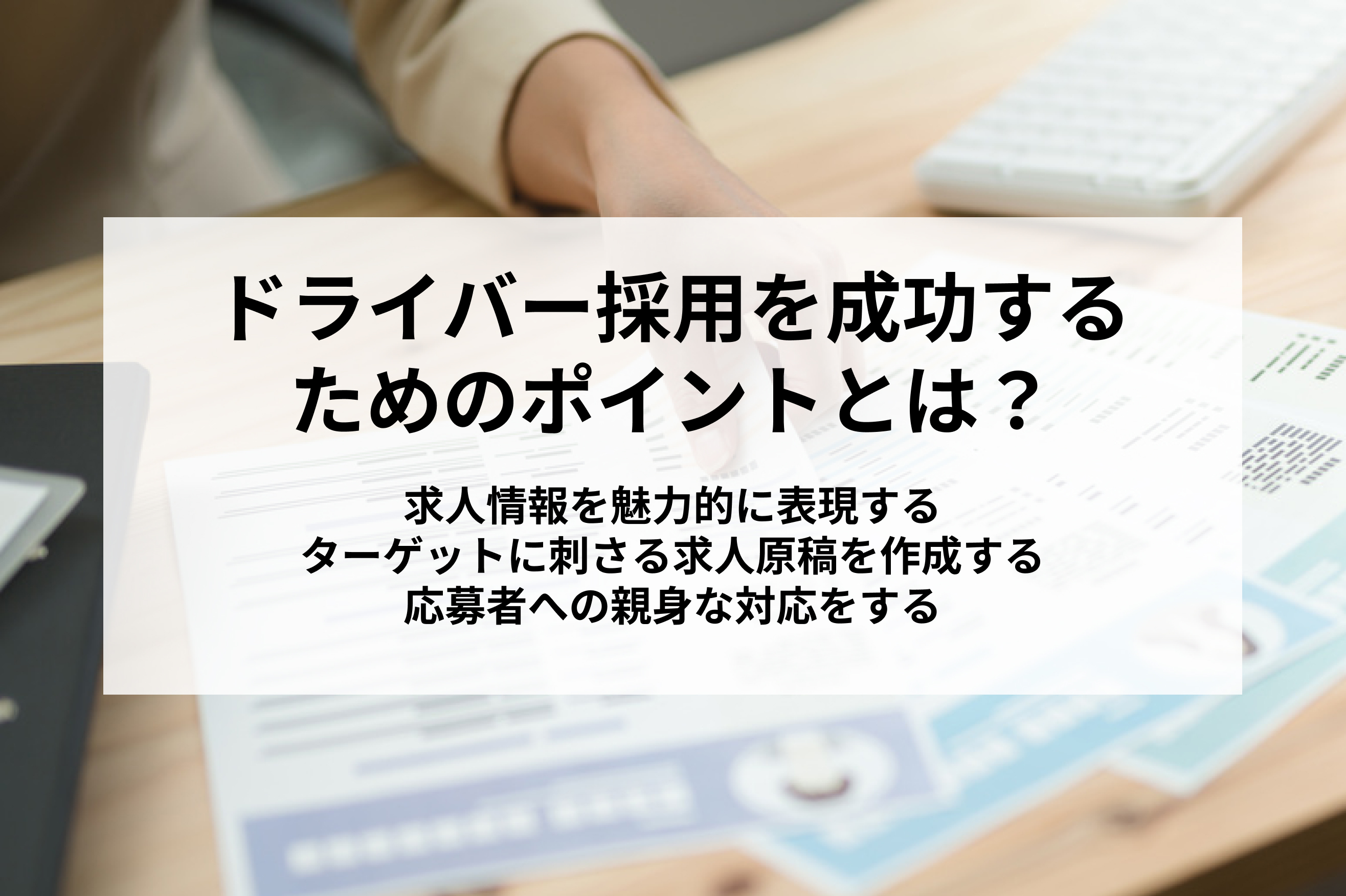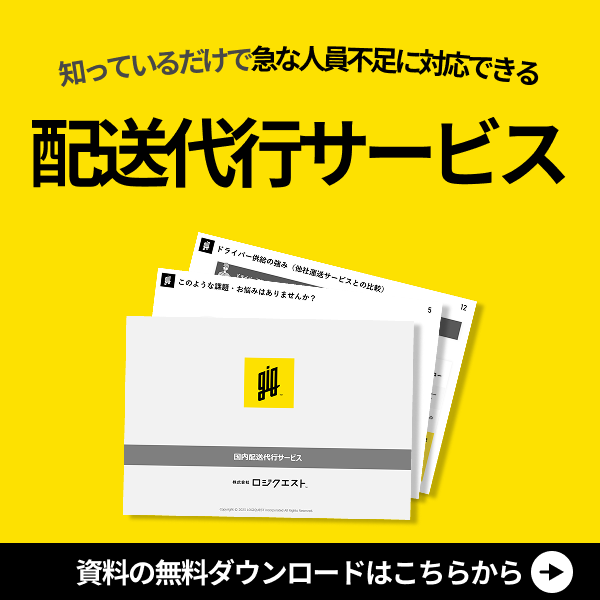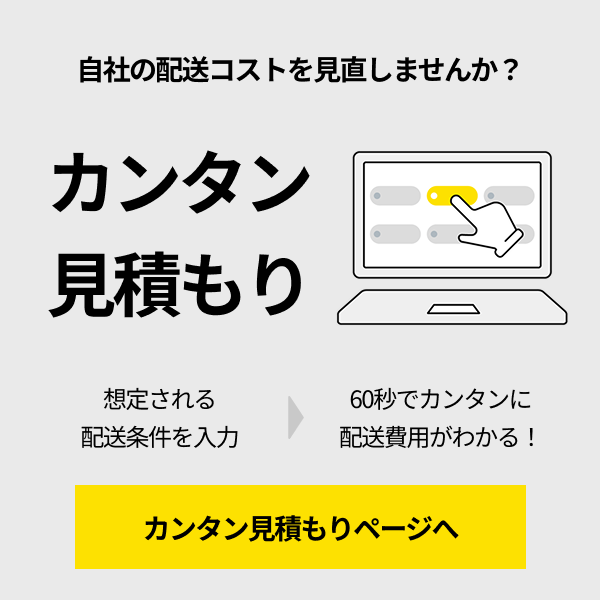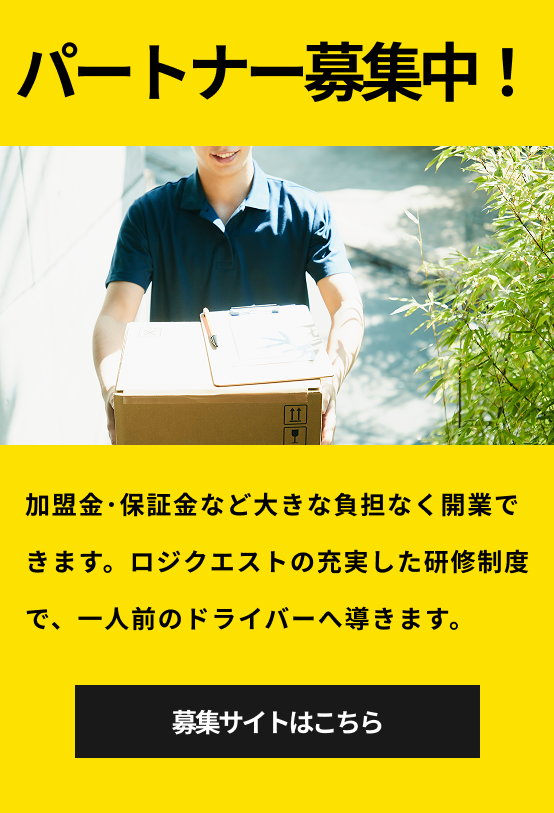配送計画システムとは?概要や活用のメリットをご紹介!
2024年12月19日
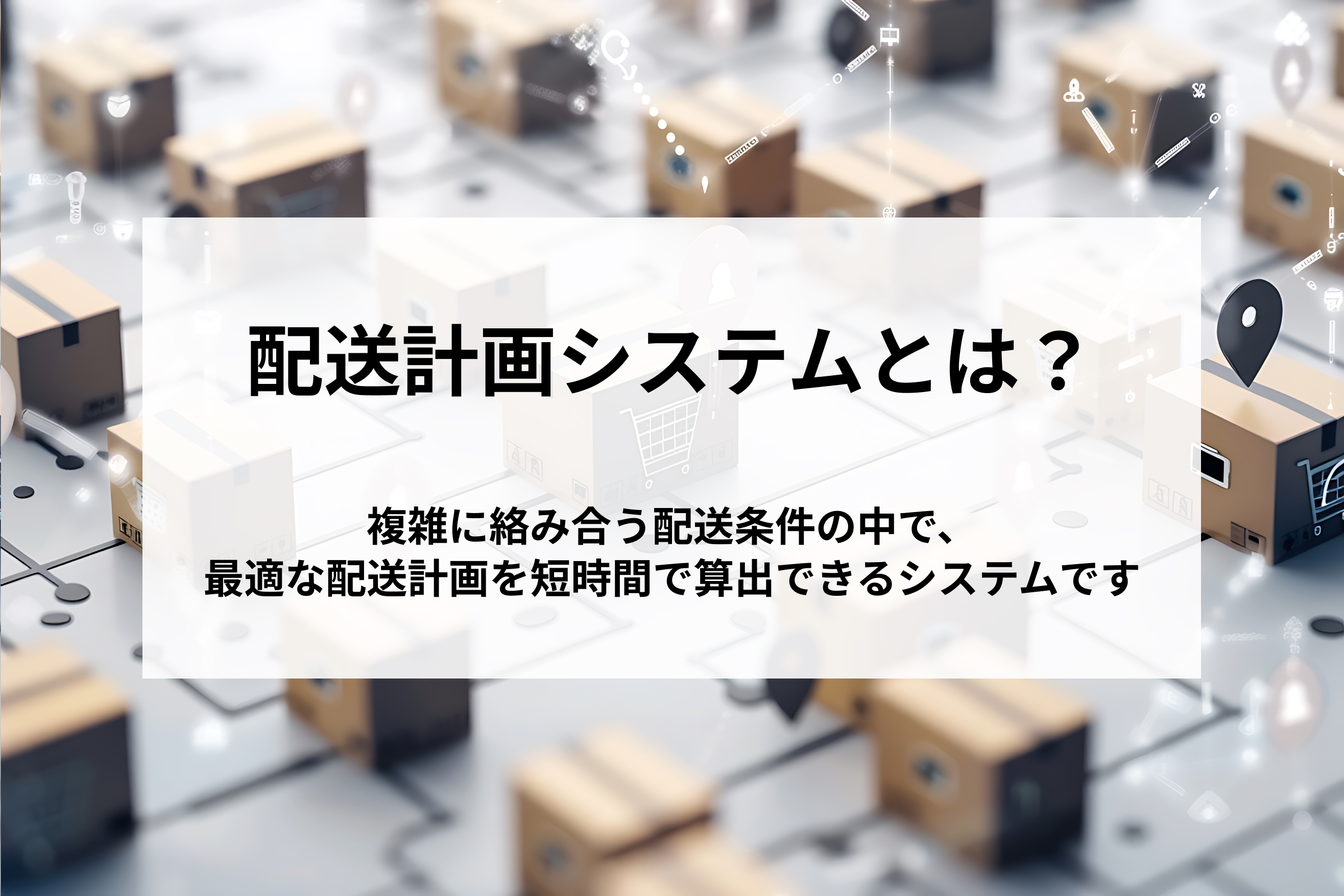
— ⏱この記事は7分で読めます —
配送計画システムをご存知でしょうか。聞き慣れない方も多いかと思いますが、人手不足が加速する物流業界において、特に効率化という点で効果を発揮する配送計画システムは、近年注目を集めています。
限りある配送リソースを効率的に配分し配送コストを抑えられることに加え、積載効率の向上や走行距離の短縮が環境負荷低減に繋がることから、配送に関わる事業者にとって見逃せない物流管理システムの一つとなっています。
この記事では、配送計画の概要や活用のメリットをご説明します。
この記事の目次
配送計画システムとは
そもそも配送計画とは
配送計画とは、交通状況や納品期限などの様々な条件を考慮し、日々の配送業務において配送リソースを最適化して示す計画のことです。具体的には、貨物量に応じた車両の必要台数を算出したり、納品先の数や場所などを基に効率的な配送ルートを考えたりと、いかに合理的に配送を行えるかを目的とした計画になります。
当然ながら、一台当たりの積載効率が最も高く、最短の配送ルートですべての納品先に届けることが出来れば、配送コストを限りなく抑えることが可能です。配送コストの圧縮は企業の利益に直結するため、入念な配送計画を立てることは重要な業務の一つです。
ただし、配送計画を最適化することは容易ではありません。
実際の配送現場では、地域の交通事情や道路特性に詳しい配車担当が長年の経験や勘所を頼りに、日々の状況に応じて作成することが多く、納品順についてはドライバーが個々に地図アプリやカーナビを使用して決めていることもあります。
配送規模が小さい場合はこうした運用でも無駄が生じにくい(最適な配送計画に近しい結果になる)のですが、納品先や車両台数の増加に比例して配送計画の最適化は困難になっていきます。これは、配送の規模が増大するにつれ、配送条件が複雑になり、結果的に検討すべき事柄が膨大になるためです。
例えば、納品先が増えると、周辺の道路特性や時間制限などの条件が複雑になり、「どの車両が、どの貨物を、どの納品先に、どのルートで配送するのか」といった膨大な組み合わせの中から最適解を選択することは非常に難しくなります。同時に、ドライバーの労働規定にも目を向けなければなりません。
こうした状況では、いくら経験のある配車担当であっても配送計画を最適化することは難しいでしょう。その悩みを解消するのが配送計画システムです。
配送計画システムとは
配送計画システムとは、複雑に絡み合う配送条件の中で、最適な配送計画を短時間で算出できるシステムです。人の手では膨大な時間が必要な計算も、こうしたシステムでは高速で行うことが可能です。
配送計画の最適化は、言い換えれば「ある配送拠点からn箇所の納品先へ、複数の車両を用いて貨物を配送するとき、様々な制約条件を満たしながら、その配送コストが最小となる配送ルートを求める」計算を実施した結果だといえます。
すなわち、その解を直ちに算出することができるのが、配送計画システムの強みなのです。
詳細には、厳密な解を導くにはシステムでもかなりの時間が必要になり、日常的に使用することが現実的ではないため、「近似解法」で解に近いものを導き出すのですが、それでも人より格段に速く、精度の高い配送計画を求めることが可能です。

ロジクエストでは配送計画システムを用いたルート最適化シミュレーションを無料で行っています。自社の配送体制を改善したい際にぜひお問い合わせください。
配送計画システム活用のメリット
では、具体的に配送計画システムを活用するとどのようなメリットが得られるのでしょうか。
配送コストの削減
最も効率的な配送計画によって、人件費や車両費、ガソリン代などの配送コストの削減が実現できます。
例えば、配送ルートが最適化された場合、各トラックの走行距離は短縮し、ドライバーの業務時間や消費する燃料の減少に繋がります。
もちろん、配送計画システムを導入する際には費用が発生します。特に、導入時の初期費用は少しばかり負担に感じるでしょう。
しかし、人による手作業では算出不可能な最適化された配送計画の下、日々の配送業務を行うことで、無駄にかかっていたとされコストが見直され、1年、またはそれ以上の長い期間で見れば確実なコスト削減が期待できます。
業務時間の短縮
配送計画システムを活用すれば、配車担当が配送計画作成に費やしていた時間が大幅に短縮され、浮いた労働力を現場のフォローやより効率化するための施策立案に充てることが可能になります。
他方では、配送計画が最適化されることによって、ドライバー一人当たりの労働時間の短縮が期待されるので、空いた時間で納品先を増やすことも可能です。
配送計画作成の標準化
必然的に経験値の高い配車担当が日々の配送計画を作成する場面が多くなるため、作成業務は属人的になりがちです。そのような状況では、担当者がやむを得ず休暇を取った場合や休職した場合などに代わりに同じ水準で配送計画を作成できる人員が必要となります。
しかし、土地勘や商習慣を加味した水準まで引き上げるには、長い期間に渡った教育の実施が不可欠でしょう。
配送計画システムを活用することで、経験値に限らず、どんな方でも同じレベルでの作成が短時間で可能となります。
導入時の注意点
配送計画システムは便利な反面、導入時には障壁があります。最後に、導入時の注意点をご紹介します。
安定稼働までの時間
当然ながら配送計画システムを初日から使いこなすことは難しく、まずはシステムに慣れるまでの時間が必要です。高齢化が進む物流業界ではとりわけ大きな障壁となるでしょう。
また、日々安定して配車するには、配送計画に関する担当者の十分な理解が必要不可欠になるので、配送計画システムの知識を習得するまでの時間を考慮した方がよいでしょう。
操作用デバイスのコスト
システム操作用のパソコンやタブレットが必要になります。異なる拠点で別の管理者がいる場合は、拠点ごとに最低1台のデバイスを確保しなければなりません。
導入に際しては、こうしたコストも発生することに注意しておきましょう。
まとめ
配送計画システムは、複雑な配送条件を効率的に整理し、配送業務の最適化やコスト削減を実現する重要なツールです。効率的な配送ルートの計算により、走行距離の短縮や燃料消費の抑制が可能となり、環境負荷の軽減にも貢献します。
また、業務の標準化を通じて属人性を排除し、誰でも高品質な配送計画が立案できる仕組みを提供します。
一方で、導入時にはシステムの習熟期間や操作デバイスの確保などの初期投資が必要であり、現場への浸透を図るための教育や運用サポートが欠かせません。これらを踏まえ、計画的な導入と現場での活用が成功の鍵となります。
ロジクエスト編集部
株式会社ロジクエストにて、国内外の輸送案件に従事する専門家メンバーが作成。
物流に関わる基礎知識やトレンドについて、分かりやすく解説しています。